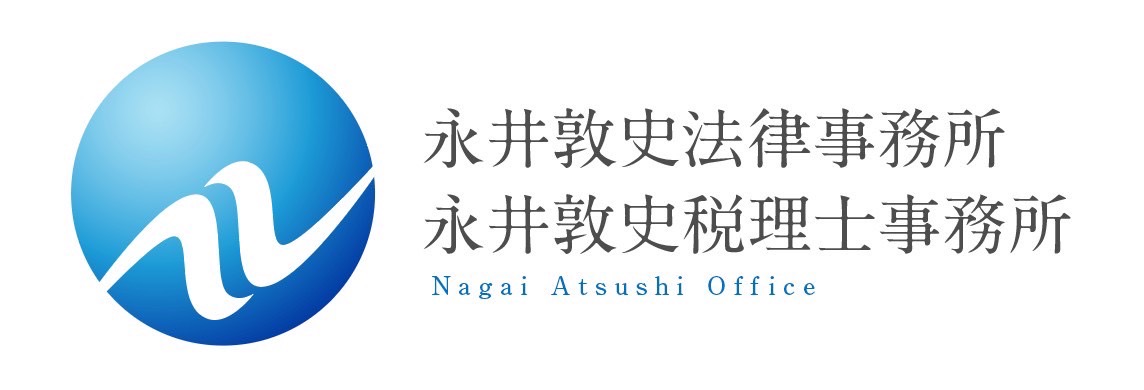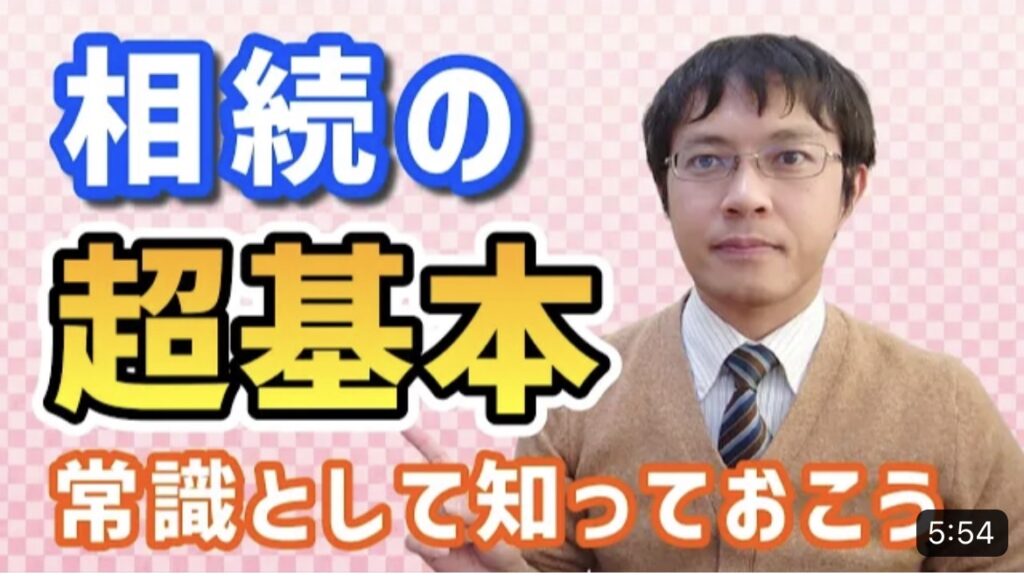相続– category –
-

戸籍謄本などが最寄りの役所で取れます。ただし、時間がかかるようです
当事務所は相続の案件を比較的多く扱っていますが、相続の場合は、相続人であることを証明するために戸籍謄本を取り寄せることが必要になります。相続の場合には、相続人本人のもの以外に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。本... -

相続放棄をしても、空き家の管理責任を負うか?
2022年に全国の家庭裁判所で受理した相続放棄の件数は26万497件だったそうです(令和4年 司法統計年報(家事編)22ページ)その理由別の件数は明らかではありませんが、他に大した財産がなく、空き家となった家を相続したくないというのも相当数あると思... -

古い抵当権を抹消するには?
たまに、自分の土地の登記にかなり古い抵当権が残ったままになっているけど、それを消したいという相談を受けることがあります。住宅ローンを返済し終えたけれども、抵当権が付いたままになっているというレベルではなく、昭和の初期やそれ以前の抵当権が... -

遺産がいくらあったら相続税がかかるか?
相続により亡くなった人から遺産をもらった場合、相続税がかかる可能性があります。ただし、遺産を取得したら必ず相続税がかかるわけではありません。亡くなった方の遺産が多くなければ相続税はかかりません。では、いくらなら相続税がかからないのかとい... -

【弁護士が解説】相続したくないときに使う相続放棄について徹底解説
https://www.youtube.com/watch?v=3B8SAASCXxI 親が借金を残して亡くなった場合には相続したくありませんよね。 そのようなときには相続放棄をしたらいいですが、注意する点もありますので、詳しく解説します。 ★目次★ ----------------------------------... -

【弁護士が解説】遺産分割のこと~問題のない場合から揉めたときまで
https://www.youtube.com/watch?v=rToqSfvMFPM&t=452s 今回は、遺産をどのように分けるかを話し合う遺産分割のことを解説しています。 ★目次★ -------------------------------------------------------------0:00 オープニング 0:25 遺産分割とな何か... -

遺産分割協議書に押す印鑑は実印である必要があるか?~印鑑に関する質問にお答えします
実印とは? 印鑑については、実印、銀行印、認め印など色んな言葉が使われます。これらは全て法律用語ではありませんが、次のように理解されています。 ① 実印 市町村で印鑑登録がされている印鑑のことを実印と呼んでいます。 実印というと、複雑... -

【相続】相続でもめる可能性があるなら、遺言を書くことを検討してください。
https://youtu.be/YM4lJvN3lDU 今回の動画では、遺産分割でもめるくらいなら遺言を書いてほしいということをお伝えしていきます。 ★目次★ ------------------------------------------------------------- 0:00 遺産分割でもめるデメリット 1:10 遺産分割... -

【そもそも相続って何?】弁護士が相続の基本的なことを解説します
https://youtu.be/Rm-odS0a4F8 今回の動画は、相続のことを余り知らない方向けに相続の基本的なことを解説しています。 中学生くらいの年齢の方でも参考になると思います。 ★目次★ ------------------------------------------------------------- 0:00 オ... -

【弁護士が解説】これだけは知っておきたい遺留分のこと
今回の動画では、遺留分について解説しています。 https://youtu.be/kenG3-tyw8w ★目次★ ------------------------------------------------------------- 0:00 オープニング 0:21 遺留分とは何か? 2:13 遺留分の留意点① 2:56 留意点② 4:13 留意点③ -----...
1